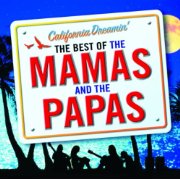非常に有名なこの銀河ですが、実際にご覧になったことがあるかたとなると、どのくらいいらっしゃるでしょうか。
アンドロメダ銀河は、肉眼で見ることができる銀河です。
ですから、望遠鏡が発明される以前から知られていた天体なんです。
ちなみに、赤道付近および南半球からは、大マゼラン雲、小マゼラン雲という銀河を肉眼で見ることができます。
さらにちなみに、ガミラスとイスカンダルがあるのは、大マゼラン雲のほうですよ。
ただ、肉眼で見ることができるとはいっても、残念なことに現代では、じゅうぶんに暗いところ、まわりに明かりのほとんどないようなところでないと見ることができません。
ですから、もしも山や海などにおでかけの機会がありましたら、ぜひさがしてみてください。
どのあたりにあるかというと、先程お話した、斗掻き星。秋の四辺形の一角から伸びている星の繋がりでしたね(南を向いて見あげたとしたら左上に向かって伸びてます)。
これを、四辺形の角から二つ辿ります。
そうするとそこから、今お話している方向で見ると右斜上に向かって星がひとつあります。
アンドロメダ銀河は、この星の少し先にあるんです。

星座が描く姿でいうと、膝小僧のあたりです。

ただし、よく天体写真で見るような、綺麗な渦巻きがたに見えるわけではありません。
ボーッとした小さな雲の切れ端のように見えます。
だいたいあのへんにあるんだな、と位置が分かったら、そこをガッ!と見つめるよりも、少し視線をずらして眺めてみるのがコツなんです。
これはなぜかというと、人間の目は視界の端っこの方が光を感じやすいんです。
銀河が放っているのはとても淡い光。
なので、もどかしいような感じではあるんですけど、そうしたほうが見つけやすいんです。
真っ直ぐには見ない、これがコツですよ。
実際に自分の目で、アンドロメダ銀河を見つけることができたら、感動しますよ本当。
さて、アンドロメダ銀河は、[アンドロメダ星雲」あるいは「アンドロメダ大星雲」などと呼ばれていた時代があります。
これは、まだ「銀河」というものが詳しくわかっていなかった時代の名残りで、現代では、同じように雲のように見える天体でも、銀河系のなかにあるものを「星雲」そとにあるものを「銀河」と呼び分けます。
したがって、いまはアンドロメダ「銀河」という呼び方が一般的です(ただ、マゼラン雲の方は、まだ、雲、という呼び方が残ってるんですね)。
この「銀河」という言葉は、ぼくたちのいる銀河系と同じようなものであるということを意味していて、イコール、銀河系の「外にある」ということです。
夜空に見えている星は、基本的にみんな銀河系の中にある星たちですから、アンドロメダ銀河はそのどれよりも遠く、それも、はるか遠くにあるんです。
比較のために、よく目立つ星のなかで遠くにあるものを探すと、たとえば、夏の大三角の一角であるはくちょう座のデネブ。
はくちょう座はまだ西の空に見えていますよ。
この星は非常に遠くにあるために正確な距離を求めることが難しいそうですが、今はおよそ1400光年離れていると考えられています。
1400光年、つまり光の速さで1400年かかる距離。
これでもすでにじゅうぶん遠いのですが、アンドロメダ銀河は、なんと、およ250万光年。
ゼロがいくつ違うんだろうというくらいに遠いんです。
光の早さでもって250万年かかる、ということは、逆に言うと、いま見えているアンドロメダ銀河は、250万年前の光がいま地球に届いたところ、ということで…、
つまり、250万年前の姿をみている、ということでもあるんです。
250万年前とは、人類はまだ旧石器時が始まるかどうかといったころ。
初期のヒト科生物である猿人の一種「アウストラロピテクス」が存在しているいっぽうで、いまのヒト属の祖先にあたるホモ属が現れてくるころ。
そして彼らが打ち砕いた小石を道具として使いだそうとしているころ、そんな時代です。
そんな、遥かな遥かな、気の遠くなるような昔の光が、今、地球に届いている…。
いかがでしょう。
そんなことを思い浮かべながら、晴れた夜には、星をみあげてみませんか。